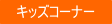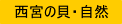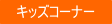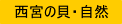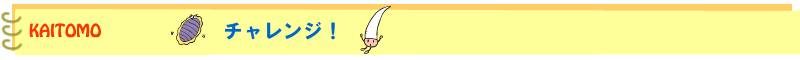 |
 |
| 貝はどんなものを食べたり、どんな風に動くのだろう。 |
| いろんな疑問を解決するには貝を飼ってみるのが一番。 |
| カタツムリや海や川の貝の飼育の仕方を紹介します。 |
| |
| ちゅうい:生きものをさわったあとは、よく手をあらうようにしましょう。 |
|
| カタツムリ タニシ アサリ |
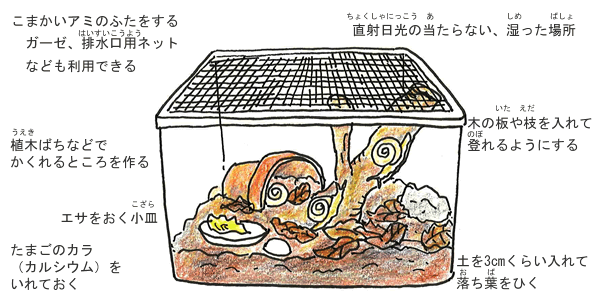 |
| 飼うときの注意 |
・カタツムリは乾燥に弱いので、湿り気を与えないといけない
・霧吹きなどして、土の表面が湿る程度に湿気を保つようにする
・カビをはやさないようにする
・食べ残しの野菜やふんをこまめにとる
・ケースについたカタツムリの粘液を拭きとる
|
| エサのやりかた |
・草食性です。新鮮な野菜(キャベツ、白菜、キュウリなど) 2、3日に1回程度
・卵の殻。カタツムリのカラはカルシウムでできているので、カルシウムが必要です
|
| 卵を産んだら |
カタツムリは一つの体でオスにもメスにもなれるので、2匹いると交尾をして産卵します。
6~8月に土の中に産卵するので卵をみつけたら、ちがう容器に入れます。
土が乾かないようにたまに霧吹きをします。1ヵ月くらいでふ化します。
|
| 観察ポイント |
・食べたものとふんの色との関係を調べる
・歯舌(しぜつ)を使った食べあとを見る
・卵を育ててみる
・冬眠させてみる
|
| 採集方法 |
・5~6月頃の雨の日や雨上がりの時に、樹木がたくさんあるところで探してみよう
・カタツムリの種類によって住んでいる所がちがいます。
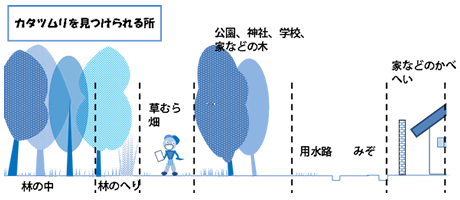
|
|
|
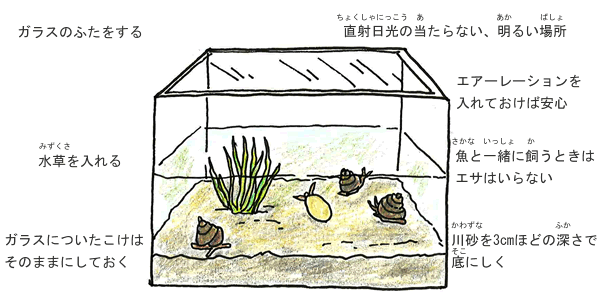 |
| 飼うときの注意 |
・タニシは田んぼや流れの無い川や池にすむ巻貝
マルタニシ、ヒメタニシ、オオタニシなどがいます。
・メダカやモツゴなどの魚を一緒に飼う(ドジョウやザリガニはだめ)
・水がよごれると、水面の方に上がってくるので、水かえをする
・タニシが死ぬととても臭くなるので、死んだらすぐに取り除く
|
| エサのやりかた |
・雑食性で魚なのが食べ残したエサを食べてくれる掃除屋さん
・少しゆがいた葉物野菜
・にぼし
・水槽のガラスについたこけ
・他の魚と一緒に飼うときは、エサはいならい
・タニシだけをかう時は、一日1~2回エサをやる
|
| 観察ポイント |
タニシは卵を産まずに、夏に、親と同じ形をした2~3mmの小さな貝を10~20個産みます。
ヒメタニシのオスの触角(しょっかく)は、左はほぼまっすぐで、右がカールしています
|
| 採集方法 |
・田んぼや水路、池など流れが無い所にいます。
・冬はどろのなかにもぐっています。
|
|
|
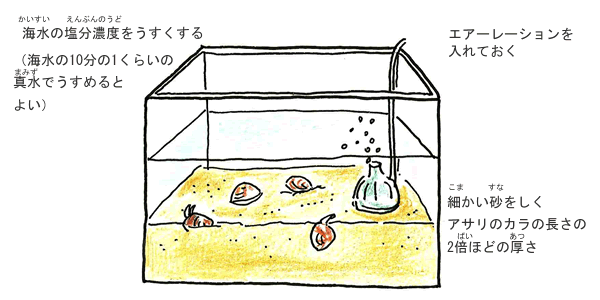 |
| 飼うときの注意 |
・二枚貝は、水中のプランクトンなどを食べているので、長期間飼うのはむずかしい
|
| エサのやりかた |
・プランクトンの代用になるエサ。人工飼料の上ずみ液を5ccスポイトで1日1回
|
| 観察ポイント |
・アサリが砂にもぐるようすをみる・水の中で、水管を出したところに色水をふきつけ、水の吸い方、はき方を観察する
・泥をまぜたえさを入れて、エアーポンプで空気を送り込み水をにごらせる。その中にアサリを入れ、水がきれいになるようすを観察する
|
| 採集方法 |
・近くに川が流れこむような、海水塩分が少しひくいところの干潟(ひがた)
|
|
| トップ |